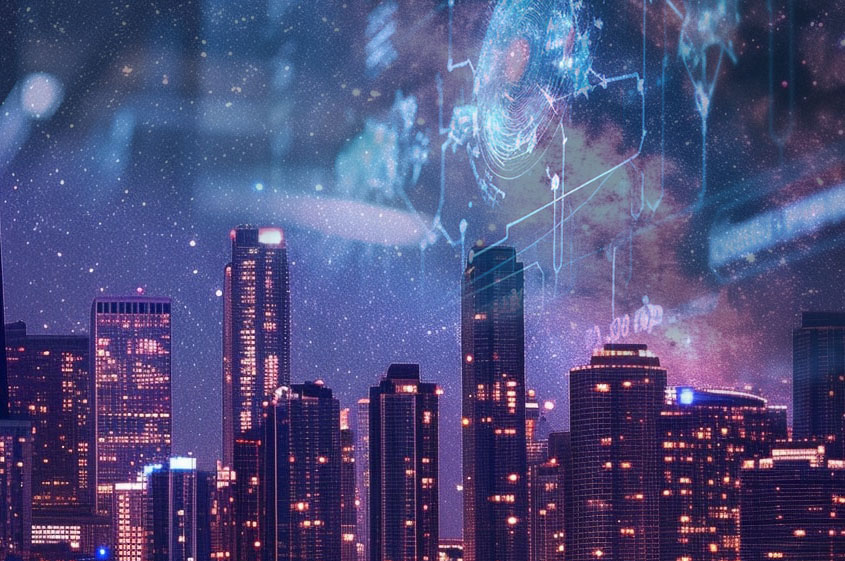
25.02.07
近年、自然災害やサイバー攻撃などのリスクが高まる中、事業継続計画(BCP)対策の重要性が増しています。
特にITシステムの導入が進む企業にとって、BCP対策は事業の継続性を確保する上で不可欠です。
今回より「企業のためのBCP対策へのクラウド活用」を全3回にわたり解説いたします。
第1回は、BCP対策をクラウドで行うことについて、そのメリット・デメリットを詳しく解説します。
BCP(事業継続計画)対策は、企業が災害や緊急事態に遭遇した際に、事業の継続や早期復旧を図るための計画および対策を指します。
これには、データの安全性を確保するシステム、迅速な復旧を支援するプロセス、そして業務を支えるリモートアクセス環境などが含まれます。
近年、BCP対策の分野においてクラウド技術が注目を集めている背景には、以下の理由が挙げられます。
クラウド環境は、地理的に分散したデータ管理、運用規模に応じたシステム拡張、迅速な導入、そして運用効率の向上といった点で、従来のオンプレミス環境に比べて優れています。
クラウドサービスは、初期投資を抑え、必要な分だけリソースを柔軟に利用できるため、コスト効率に優れています。
クラウドプロバイダーは、高度な冗長化技術や可用性対策を講じているため、オンプレミス環境よりも高い可用性を期待できます。
クラウドプロバイダーは、セキュリティ専門家を擁し、最新のセキュリティ技術を導入しているため、一定レベル以上のセキュリティを確保できます。
これらの理由から、多くの企業がBCP対策にクラウドを活用するようになってきています。
ただし、クラウドを活用する際には、ネットワーク接続の問題やセキュリティ対策など、いくつかの注意点も存在します。
これらの点を踏まえ、自社の状況に最適なBCP対策を検討することが重要です。
近年、自然災害やサイバー攻撃などのリスクが高まる中、事業継続計画(BCP)対策の重要性が増しています。
特にITシステムの導入が進む企業にとって、BCP対策は事業の継続性を確保する上で不可欠です。
ここでは、BCP対策をクラウドで行うことについて、そのメリットを以下にご紹介します。
クラウドを活用することで、企業の重要データを堅牢なデータセンターで管理できます。
地震だけでなく、火災や停電にも強い構造のため、自社でサーバを保管するよりもデータ消失リスクを大幅に軽減できます。
多くのクラウドサービスでは、バックアップ機能や冗長化構成を標準で備えており、迅速なデータ復旧も可能です。
万が一の事態が発生した場合でも、データ消失の心配なく、速やかに事業を再開できます。
AIエンジニアやデータサイエンティストなど、AI、IoT、クラウドなどの先端技術を活用できる人材
クラウド環境では、インターネットさえあれば、どこからでも業務に必要なデータやシステムにアクセスできます。
災害で出社が困難な場合やオフィスが倒壊して利用できない場合でも、クラウドサービスを利用すれば安全な場所で仕事を続けることが可能です。
テレワーク環境の整備にもつながり、従業員の安全確保と事業継続の両立が実現します。
従業員は、自宅や避難先など、安全な場所で業務を継続できます。
クラウドはオンプレミスに比べて、初期投資を低く抑えられる点が大きな魅力です。
必要なスペックを限定して必要な分だけ利用することで、無駄なコストを削減しながら、スケーラブルな環境の構築が可能です。
BCP対策の必要性を感じていても、実際はコスト面が課題となり、BCPを策定していない企業も少なくありません。
そのため、コストパフォーマンスの高さは重要なポイントと言えるでしょう。
クラウドを活用したBCP対策は、事業継続性を高める上で有効な手段ですが、利用にあたっては以下の点に注意が必要です。
大規模な停電や広範囲なネットワーク障害が発生した場合、データセンター自体が無事であっても、データへのアクセスが困難になる可能性があります。
また、データセンターも自然災害などの影響を受ける可能性があり、事業継続が完全に保証されるわけではありません。
そのため、データの保管場所を分散したり、ネットワーク障害時の代替手段を確保しておくことが重要です。
クラウド上に機密情報を保管する場合、情報漏洩のリスクが常に存在します。
クラウドサービスのセキュリティ対策が不十分な場合、サイバー攻撃の標的となる可能性もあります。
そのため、信頼性の高いクラウドサービスを選び、データ暗号化やアクセス制限などのセキュリティ対策を講じることが不可欠です。
この記事は、次回「企業のためのBCP対策 第2回:クラウド活用の構築手順」に続きます。